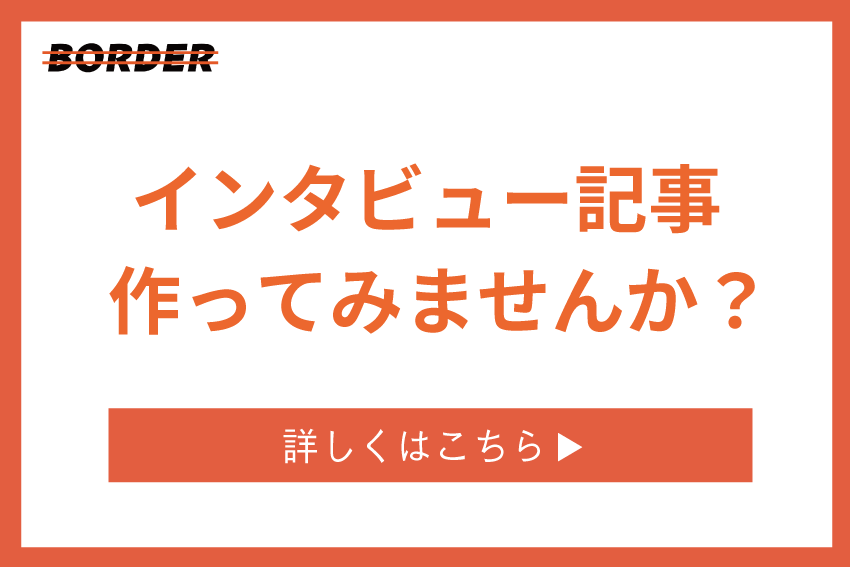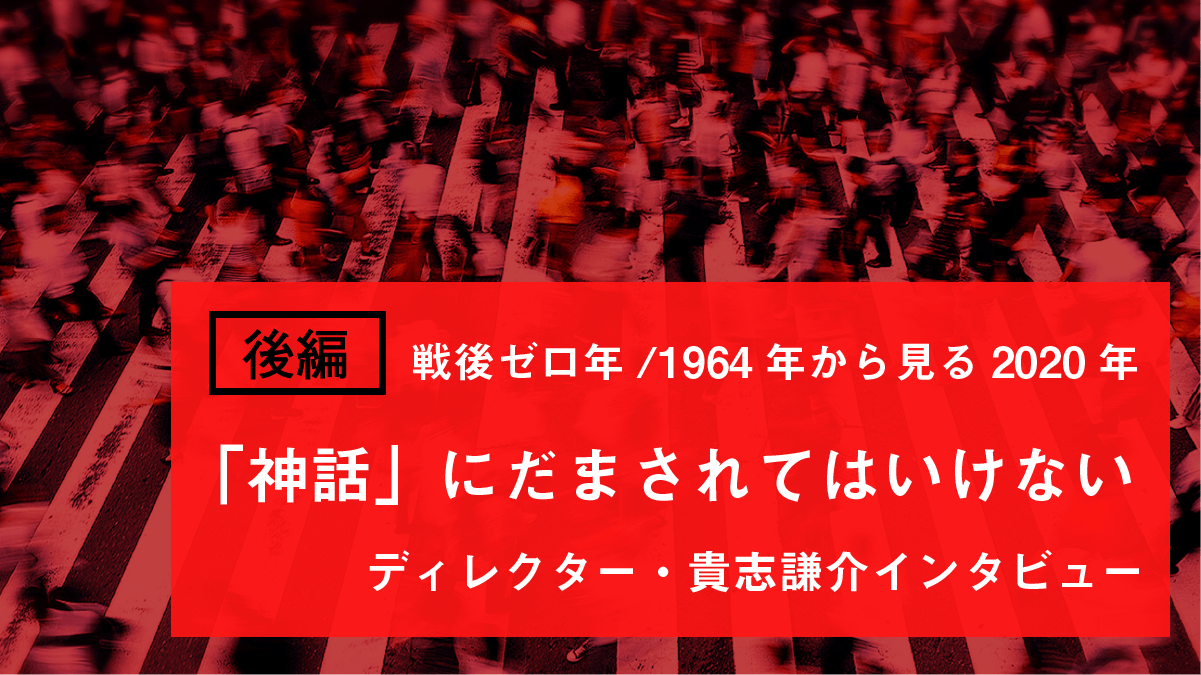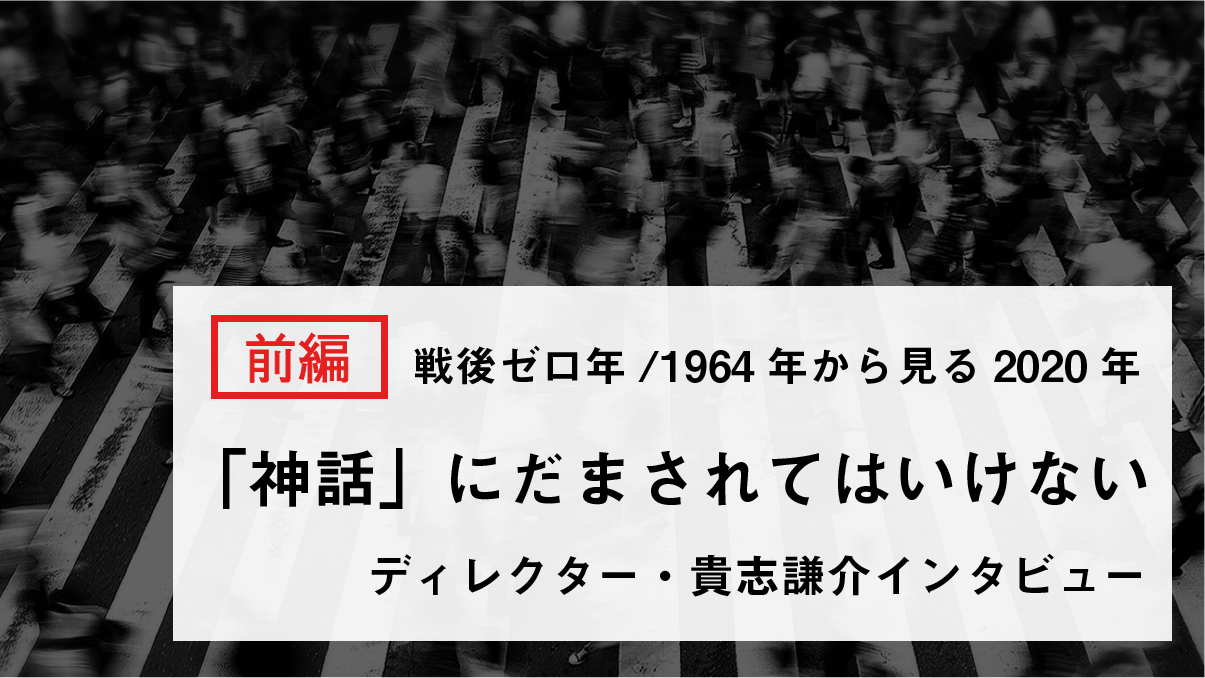真剣に面白いを考えた先にヘンがある—映像作家・藤井亮インタビュー
映像作家の藤井亮さんが世に放った作品はどれも「ヘン」で面白いものばかりだ。2016年に公開された戦国武将の石田三成が突如現れコミカルに踊る「石田三成CM」は、実は滋賀県のPR映像として制作された。そして今年1月放送、乃木坂46のメンバー10名と気鋭の映像作家10名がタッグを組んだオムニバスドラマ・シリーズ「乃木坂シネマズ」ではシリアスな作品が多く並ぶ中で、乃木坂46松村沙友理さんとのタッグ作品「超魔空騎士アルカディアス」が一際に異彩を放っていた。アナログで遊び心が溢れていているけれど、どこか狂気を感じる「ヘン」な映像を生み出し続ける藤井亮さんに、どうしたら面白いものをつくることができるかを聞きました。
※この記事は2020年3月17日に取材したものです。
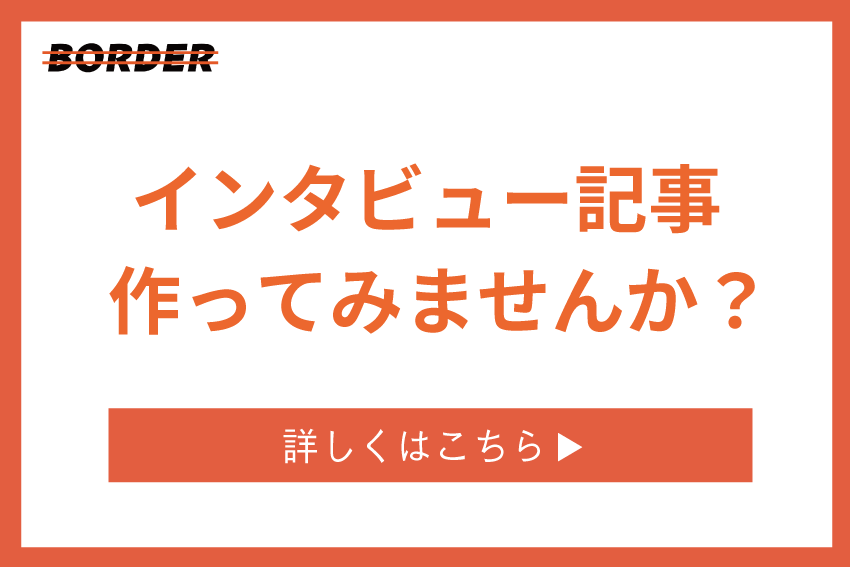
「遊び」から仕事へ
―なぜ美術大学に進学されたのでしょうか。
藤井:高校までは愛知県の半田市に住んでいて、地元のそれなりの進学校に通っていました。中学時代は真面目に勉強を頑張っていましたが、高校に入った途端に学年で下から三番目くらいまで成績が急に下がってしまったんです。それで勉強が嫌になって、逃げるようにノートとか教科書にずっと落書きをしていました。そんなことをしているうちに進路を決める時期がやってきて。これから自分は何で勝負をしていくのかを考えたときに、勉強で勝負するのは無理だと思ったけれど、絵を描くことは周りの人たちより得意だなと思いました。こんな片田舎の高校の中ですら、すでに僕より勉強ができる人はたくさんいるけれど、僕より絵がうまい人はいなそうな気がする。それならまだこっちで勝負したほうがマシじゃないかなと。
―才能を信じて、アートの方面で勝負していくことを決意したのですね。
藤井:そんなに大それたことではなかったのですが、作家とかアーティストになるほどの自信はまったくなかったので、デザイナーとかで仕事としてアート方面に進んでいきたいなと漠然と思っていました。

―そして武蔵野美術大学デザイン科に入学。美大ではどのような勉強をされていましたか。
藤井:美大の授業って僕にとって遊びの延長線なんですよ。真面目に勉強するためというよりも、基本的には大学には何かをつくりにいくために通うんです。朝に大学へ行って、何かをつくって帰ることの繰り返し。今の僕が仕事としてやっていることと全く変わらない感じなんです。勉強をしに行くというよりも遊びに行っていたような感覚ですね。
―藤井さんは映像作家として活動されていますが、大学時代には映像をつくられていたのですか。
藤井:もともとはデザインやグラフィックをやろうと思っていたので、映像を学ぶために入学した訳ではないのですが、いつのまにか映像の方が楽しくなって自然に映像をつくるようになりました。きっかけは映像をつくって発表する講義でした。1グループ5〜6人で映像を協力してつくって、毎週1グループが発表するのですが、僕たちがつくった映像が会場でめちゃくちゃウケたんです。一見シリアスな刑事ドラマなんだけれど、実はやっていたのは缶蹴りだったというしょうもない内容で。今まで自分がやっていた絵とかデザインは作品を見た人の反応をダイレクトに見ることが難しかったけれど、映像は見た人の反応がはっきりとわかる。自分たちのつくった作品で目の前のオーディエンスがドワッと盛り上がっていくのは刺激的だったし、その感覚は今でも覚えています。
―学生時代はどのように過ごしていましたか。
藤井:こどものような遊びを本気でやっていました。グラウンドで本気で「だるまさんが転んだ」をやってみたらどうなるかとかやっていましたね。みんな自分の体を丸々隠せるような大きい板とか箱を持ってくるから誰が誰だかわからない状況になるんですよ。あとは、大学がある国分寺全域を使って50対50のドロケイをやったり、学園祭の時は大学の入口に巨大なロボの頭をつくるみたいな変な展示を毎年やっていましたね。美大生って同じような感覚の人が集まっているから何かをつくったり、始めたりするときに話が通じやすいんですよ。やっていることはくだらないことでも、「面白い」という感覚を見栄えとかビジュアルのイメージを通じて共有できていたのかもしれないです。
企画を考える日々から念願の制作へ
―どのような経緯で関西電通に就職されたのでしょうか。
藤井:ある意味、逃げの発想で広告代理店を選んだんですよ。仕事でも映像をつくりたかったのですが、当時は言葉を使う表現に自信がなかったんです。いきなり2時間の映画をつくるほどの実力はなかったし、制作会社に入っても長い下積みが必要そうだし、テレビ局のバラエティみたいな世界には向いている気がしなかったんです。でも、当時つくっていた映像は5分以内の短い映像ばかりだったので、尺が短ければストーリーのある面白い広告を自分でもつくれるんじゃないかなと思って関西電通を受けてみました。
―関西電通ではどのような仕事をされていたのですか。
藤井:入社してからはCM の企画をずっとやっていました。 CM の絵コンテをたくさん書いて、クリエイティブディレクターに見せてボツを何度も貰うのを繰り返して、やっと通った企画をクライアントにプレゼンして、プレゼンが通ったら制作会社の人に制作をはじめてもらい、こっちはそれをチェックする、みたいなことを10年くらいやっていました。ただ入社後に気づくのですが、広告代理店は企画を考えるだけで制作はやらないんですね。今思うと、素直に制作会社に入った方が制作に携われたのかもしれないです。
―今は広告代理店でも制作を担っているイメージがありますが、当時は企画立案が中心だったのですね。
藤井:僕が入社した当時は、まだ広告業界が強気な時代だったんですよ。代理店はあくまで企画を考えるだけで、「制作は制作会社に任せるのが正しい」という不文律があったんです。代理店の人間は企画をどんどん考えて制作会社に仕事を割り振って案件を多くこなすことをよしとする空気感。今だったら考えられないけれど、自分で広告物を制作しようとすると怒られたりしました。まあビジネスとしてはそっちの方が正解なのかもしれないのですが。
―藤井さん自身がやりたかった制作はいつからやり始められましたか。
藤井:代理店で10年もやると自分で自由に決めて動かせる案件が増えてくるんです。チャンスだなと思って、ここからは企画も制作も全部自分でやっていこうと思いました。でも、会社側としては誰もお前にCMディレクターをやってほしいとは言っていないし、制作会社としても制作に代理店が入られたら困られる。そういう縄張り意識があったので、僕が手を動かすことが求められていなかった。それはちょっとしんどかったですが、少しずつ自分でやる範囲を広げていきました。
自分の手でつくり出した「ヘンな」広告
―代理店時代に「石田三成CM」や「宇治市PR動画」「サウンドロゴしりとり」などの広告を制作。藤井さんの作品はどれもユニークですが、どのように「ヘンな」作品をつくるのですか。
藤井:低予算でどれだけインパクトを残せるのかを考えていった結果なんです。膨大な予算があって、労力を割けばハリウッド映画みたいなクオリティのCGで勝負をすることができるけれど、お金がなければ、Playstation 1くらいのCGしかつくることができない。お金がなくてもつくれる面白いことを探していった先に、逆にPlaystation 1くらいのCGをあえて使ってネタにできれば勝負ができるんじゃないかと考えました。

―まさに逆転の発想ですね。藤井さんが制作される作品にはアナログ感やレトロ感が感じられるものが多いです。
藤井:自分が最も影響を受けた時代の空気感を作品にも自然に取り入れちゃうんじゃないのかなと思います。小中学生の頃に何気なく触れていた変なローカル CM は「石田三成CM」に通ずるし、スーパーファミコンは「宇治市PR動画」に活かされている。子どもとか学生の頃までのストックが活きている実感はありますね。
―逆に新しいものからインスピレーションを受けることはありますか。
藤井:もちろん新しいものからもいろいろな刺激をもらっているし、大まかな流行りくらいは押さえておくべきだと思いますが、制作していく上で極論流行りは追いかけなくていいのかなという気はしています。今の若い子の間で流行っているあれこれを取り上げるだけでは既にその流行りの二番煎じになっているわけだし、あまりかっこいいものではない。むしろ流行りとは一切関係のないものを取り上げた方が面白くなることが多いですよね。例えば、全然流行っていない縄文土器を取り上げてみる方が結果的に若い子が面白がってくれるかもしれない。ものをつくるなら「みんながそれをやるなら、私はこっちをやる」みたいな感じでいいんじゃないでしょうか。

―ひと昔前のブラウン管のテレビの映像っぽい雰囲気をつくるために、あえて一度映像をVHSに焼いてさらにそれをデータ化をすると伺っています。アナログな質感をつくりだすためのこだわりが感じられます。
藤井:こだわるという意味では、自分が安心したいからだと思います。作品の細部まで自分の納得がいくまで手間をかけることでクオリティに自信が持てる気がするんです。Mac上でAfter EffectsとかPremierを使ってそれっぽいものをつくろうとしても、味が出てこないし限界があります。だから1回アナログな過程を通さないとどうしても不安になってしまうんです。自分の手間をかけるのはタダですし。
過度にターゲットを想像しない
―2019年1月には関西電通を退社しフリーランスとして広告以外の映像制作に携わっていますが、今年放送されたフジテレビ系列の「乃木坂シネマズ」にも映像作家として参加されています。どのような経緯で依頼されたのでしょうか。
藤井:プロデューサーから、乃木坂46のメンバーから1人を選んで30分の尺でストーリーをつくってくださいと一任される感じでした。基本的にはディレクターごとに任せてつくってもらうというルールだったので、何の縛りもなかったです。
―ちなみに主役として松村沙友理さんをなぜキャスティングしたのですか。
藤井:プロデューサーに誰がおすすめですかと聞いて、松村さんを勧めていただいたんです。演じるのが少し大変な役だとは思ったのですが、意思疎通が取りやすかったので助かりました。
―「超魔空騎士アルカディアス」はいわゆる長尺で、代理店時代の広告作品とはスケールが異なる作品ですよね。
藤井:もともと15秒とか数分間の尺の広告制作が本職だったから、30分の尺の映像作品はまるで競技が違うんですよ。二時間くらいの映画がフルマラソンなら、30分の映像作品はハーフマラソンで、十数秒から数分間の映像は短距離走、というくらい違うんです。それに僕は根っこが演出家ではないので、セリフの機微とか感情の微妙な動きで勝負するのは苦手なんです。だから自分が勝負できる土俵をつくらなきゃいけないなといつも考えています。
―どのように土俵をつくるのですか。
藤井:シチュエーションをそもそもおかしくすることを意識しています。本当に脚本を書くのが上手い人なら、普通の若い男女が椅子に座って喋っているだけでも面白い話をつくれますよね。僕の場合は座るところを椅子じゃなくて便器にしてみたり、背景にタンスの代わりに仏像を並ベてみたりして根本をずらすようにしています。根本が変だとどれだけ上に真面目なものを積み重ねても変であることはゆるがないので、そこから面白さを見つけていこうと考えています。

―作り手側の面白さの基準と鑑賞者の面白さの基準は違うと思いますが、そのギャップをどのように埋めるのでしょうか。
藤井:僕自身、制作物のターゲットをあまり意識していないんです。もちろん仕事だからふわっとしたターゲットは設定されているけれど、そもそも一言で括れてしまうようなターゲットは都合良く存在するわけがないんです。例えば30代男性のイメージは存在しても、人によって好きなものも生活スタイルも違うわけでそのイメージを地で行くような人はいないですよね。だから、まずは自分の感覚を大事にしています。あとはターゲットが30代男性だったら、周りにいる30代男性の友達が見て面白いと思ってくれるかどうかで考えています。
真剣に面白いものをつくろうとすると、人は根暗になる
―制作する中で絶対にこれが面白いと思える自信はどこから生まれてきますか。
藤井:そういう自信は全くないです。つくるときは常に悩んでいるし、制作物が完成してからもずっと不安なのは変わらないんです。 誰かが制作物を見て「面白いですね」と言ってくれても、実は気を遣ってくれているだけなんじゃないかと思ってしまいます。それに、自分がパッと思いついたものに変に自信を持ってしまうと、そこから作品を良くしていこうと考えなくなってしまう。不安なままでいいんじゃないでしょうか。ものづくりに関わる人は自己肯定感が強くない方がいいし、むしろ自信を持つ方法なんか持たない方がいいのかもしれません。
―世の中的には自信や自己肯定感をつける方法が求められていますが、逆に持たない方がいいと。
藤井:自己肯定感なんかそんなにつけなくても大丈夫。自己肯定感がなくても生きていけるから。
―大人になると、そういう漠然とした絶望感は感じなくなると言われがちですが。
藤井:それはその人が諦めているからかもしれませんね。焦ったり怖がることに疲れて考えたり手を動かすのをやめようとするから「大人」になってしまうんですよ。正直、生きていく上では「大人」になってしまった方が楽だと思います。でもものづくりの現場にいる人は、何がウケるのかが分からない怖さを感じ続けると思います。もしも何かをつくることで生きていきたいと思うのなら、たとえ60歳になっても本当にこれでいいのかなと悩みながら手を動かし続けなくてはいけないと思っています。

~お知らせ~
現在NHK Eテレにて放送中の「オリンピア・キュクロス」も藤井さんが制作されています。あの「テルマエ・ロマエ」の作者ヤマザキマリさんが現在グランドジャンプにて連載中の漫画のショートアニメで、ギリシャ・オリンピアから裸で走る男が1964年の日本へ突如タイムスリップする作品で、本アニメでは古代ギリシャのパートをクレイアニメーションで、日本パートを紙芝居アニメーションで制作されています。古代オリンピックと日本文化を比較し、そこから派生する人間の悩みについて哲学的に考える、前代未聞の痛快比較文化コメデイとなっています。インタビューで紹介した藤井さんの作品と同じくらい、それ以上に斬新で「ヘン」な映像体験を是非お楽しみください。
第一話はこちらから↓
ニコニコ動画
https://www.nicovideo.jp/watch/so36685284
取材・文/伊藤勇人 撮影/伊藤拓海