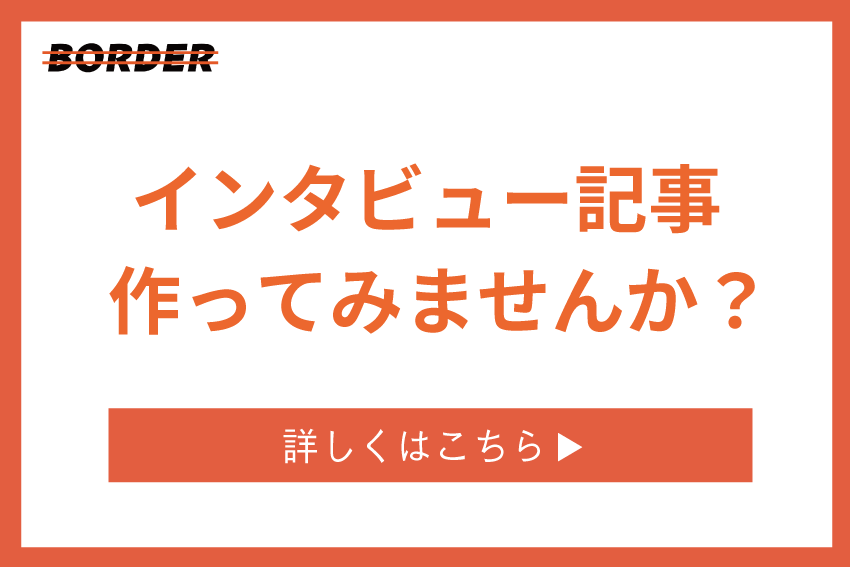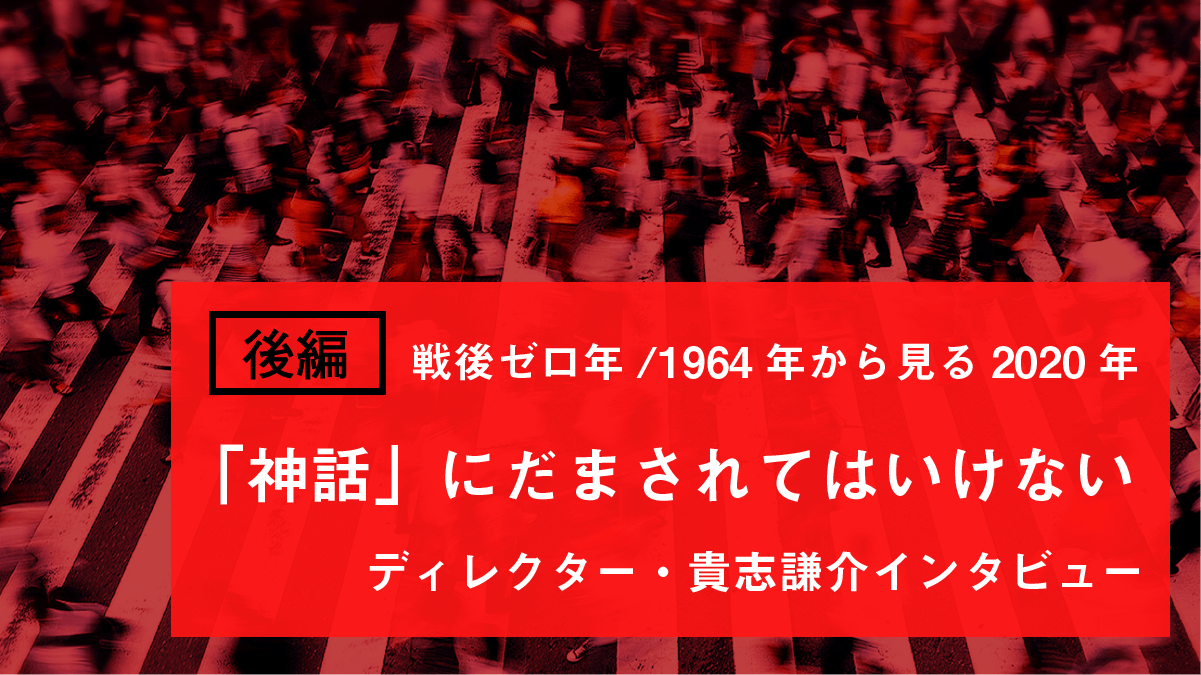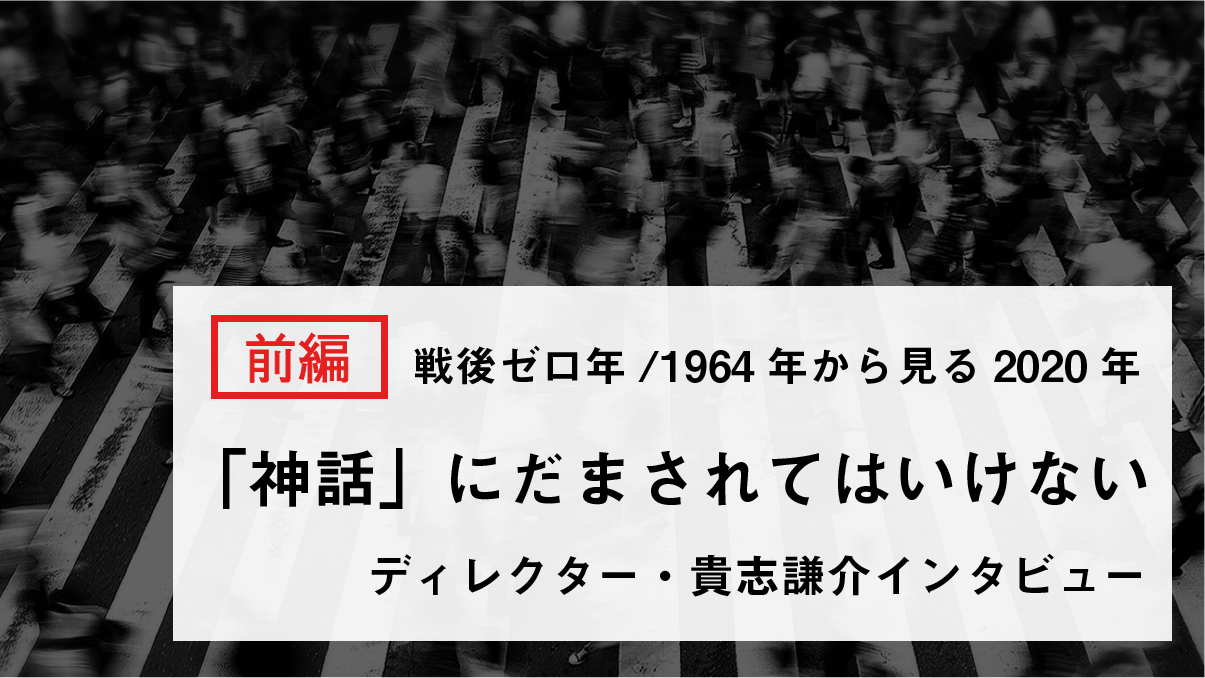ボーダーの外側へ テレビ東京ディレクター上出遼平インタビュー(後編)
テレビ東京ディレクターの上出遼平さんが世に放った「ハイパーハードボイルドグルメリポート(以下、ハイパー)」は、僕たちの日常とはかけ離れた遠い世界を映し出した。ヤバい国のヤバい人たちの生活や食事に密着する中で自身の価値観や倫理観が絶対的ではないことを思い知らされる。テレビが好きではなかったと語る彼は番組を通して視聴者に何を問いかけているのだろうか。
後編では、ハイパーの構想の裏側と旅をする意味を訊きました。
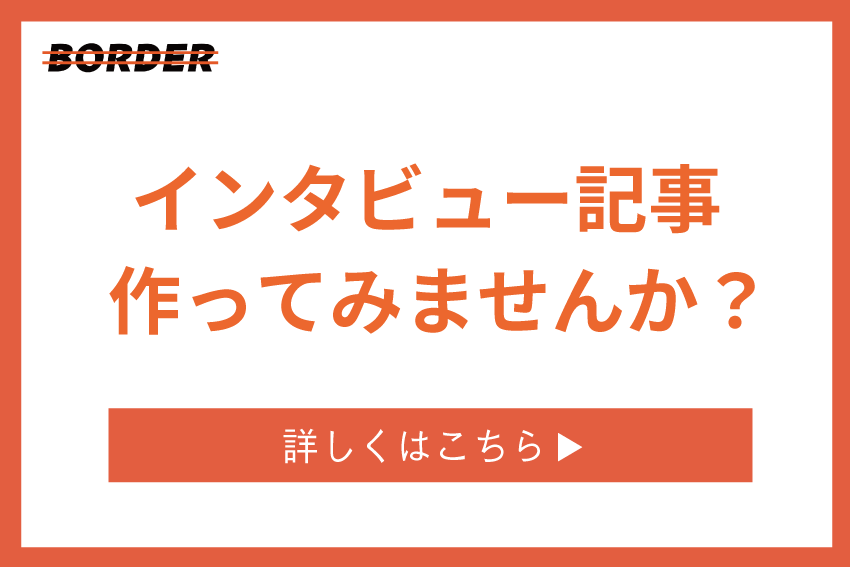
エンターテイメントで問う

—そもそもハイパーのようなハードボイルドな番組を構想された経緯はどのようなものだったのでしょうか。
上出:今までにないものを生み出すには、自分にできるものはなんなんだろうかっていうことをまず考えなくてはいけないわけですよね。自分のポテンシャルを総動員して、社会にまだ気づかれていない隙間の部分を探すわけで。それで、自分にしかできないことはなんだろうかと考える。僕が経験してきたことといえば、人が踏み入らないところに行って生きて帰ってくることだったんです。僕は物心つく頃から一人でテントを背負って山に入っていたし、世界中の僻地でカメラを回してきた。それはソファに座ってポテチを食って腹出してるテレビマンにはできません。だから僕には、インドア系テレビマンにできないことができるなっていうのがまずベースにあって。それに加えて、学生時代の事をお話しした時にも触れましたが、”BORDER”を引くこと、その”BORDER”が唯一無二のものであると思い込んでしまうことに対して問いを投げかけたいという思いがずっとあって。じゃあ、僕が今まで行ってきたような場所で何を撮って何を表現することができるんだろうということを考えて、辺鄙な場所のヤバい人たちと飯を食ってくるっていうところに行き着いたんです。
—なぜ食をテーマとして置いたのですか。
上出:「境界を問う番組」なんて掲げたって誰も見てくれません。押し付けがましくって勉強くさい。僕たちが作るものはエンターテインメントでなければならないんです。それができるのがテレビマンの唯一の強みといってもいいかもしれません。じゃあどうするか。ヤバいところに僕が入っていくっていうエンターテイメント性ももちろんあるんですけど、それじゃクソほどある番組と同じじゃないですか。だから「飯」を合わせた。僕が世界の飯は面白いんだってことを知っていたからでもあるし、同じ釜の飯を食わなきゃ深い話ができませんよねっていう日本ならではの考え方もあって。一回目の放送では、少年兵とかギャングとかマフィアとか、人殺ししか出てこないんですよ。もしも隣りに人殺しがいたらもちろん怖いじゃないですか。極悪人にしか見えないじゃないですか。でも実際に一緒に飯を食ったらどうなんだろうって。「人殺し」の向こうの人間が滲み出てきて、本当にその人は真っ黒なんだろうかっていう問いが出てくるんじゃないか、っていう発想もありました。
—食を通じて生活の様子や人となりが見えてくることもありますね。
上出:例えばスラム街での人々の生活なんて、僕らが実際に目にすることってないじゃないですか。でも彼らの生活だって僕らと地続きの世界で営まれているんですよ。彼らは、お金がなくてその日の飯しかないのに楽しそうに生きている。それを視聴者に見せられたら、消費社会における幸せに対する思い込みなんて、一時的かもしれないけど簡単に崩せるとも考えていました。

―ハイパーの番組内では、密着に応じてくれる現地の方が「一口食べるか?」と食事を分けてくれるシーンが印象的です。
上出:単純にみんな親切なんですよ。本来そういう優しさは人間にとって当たり前のことで、不思議に思えるのであれば、利益衡量でしか思考できなくなってるのかもしれませんね。それでも、彼らからもらう一口っていうのは東京でもらう一口と重みが全く違いますが。
—言われてみればそうかもしれません。
上出:僕らが社会的に立場の弱い人たちにカメラを向けて、最後には打ち解けて一口もらうことがどうして許されるのかといえば、やっぱり彼らに語りたいことがあるということに尽きると思います。それがなかったら僕のやっていることは暴力で、勝手に撮影したものを放送してお金を稼ぐことは収奪でしかない。彼らには伝えたいことはあるけれど伝えるための場所や術がない一方で、僕にはカメラという世界に伝える手段があるという点で、利害が一致している部分がある。例えば、ギャングとかマフィアって呼ばれる人たちはメリットもないから、テレビにあまり出てくれないんですよ。ただ黒人ギャングは、メディアが好き。オンエアではほぼカットしているけれど、カメラを向けるとすぐラップするんですよ。彼らの中からケンドリック・ラマーみたいなビッグスターが生まれるんだから、みんなチャンスを狙っているんだと思います。
―届かない声や見えないところにスポットライトを当てることがメディアが果たす役割のひとつだと思います。ハイパーはそういった見えないものをエンターテイメントを通じて可視化しているのですね。
上出:僕はバラエティ担当の部署なので、基本的に営利目的がメインなんですよ。一方で報道は利益度外視で国の暗部や秘密を暴くようなことをするべきじゃないですか。けれど現状はそうではなくて、ワイドショーなんか見れば、少しでも規範を逸脱した人間を過剰に取り立てて騒いでいるだけというか。当然テレビマンなので僕はその片棒を担いでいるわけですよね。僕はその状況が恥ずかしいと思っています。僕らテレビが、人の視線をどうでもいいことに向けさせて、巧妙に世の中の臭いものに蓋をしてるんです。その状況で世の中の隠されているものを視聴者に届けるためには、それをエンターテイメントに紛れ込ませて、周到なオブラートに包む必要があるんですよ。
ハイパーハードボイルドバックステージ
―放送後、視聴者の方からはどのような反響がありましたか。
上出:一番嬉しかったのは、普段テレビを観ない人たちが見てくれたことです。特にNetflixに番組のアーカイブを出してからの反響がすごいです。Netflixでこの番組を見て、最後に「製作テレビ東京」って出て驚いた人が多かったそうで、すごく嬉しかったです。
―自分たちの日常とは程遠い未知の世界に飛び込んでいくのは勇気がなければ難しいと思います。
上出:勇気なのかなぁ。僕は興味の方が勝っちゃうんですよね。でも、なんでそこまでリスクを取れるのかというと、明日死んでもいいって思って生きていたいからですね。リベリアに行った時には、ここで面白い映像が撮れないなら死んだほうがいいくらいだと思いました。テレビ制作で命を懸けるなんてことがあってはならないんですけど、命を半ばかけても満足できる映像を撮りたい。「あそこでもう一歩踏み出していたら」って後悔して帰国する自分が嫌なんですよ。リスクを背負ってでも、納得のいくものを作りたい一心です。

—リベリアの内戦時に少年兵だった人たちが住む墓地に入った際に、彼らにカメラを強奪されたり、ポケットからテレ東のボールペンがすられるシーンは今までのテレビ番組では見ることのないような生々しさを感じました。
上出:あれは震えるよね(笑)。
―手持ちのカメラから見える主観的な映像が没入感を感じさせる分、見ていてとても怖かったです。一方で自分はこの危険な状況を安全に味わうだけで、どうしようもない気持ちになりました。
上出:そういう風に思ってもらえたら本望ですね。自分だけが安全圏からその世界を見ているっていう構図に疑問を持ってほしくて作っているところもあるし、僕自身、結局どこまでいっても安全圏から見ているんですよ。だけどそこから僕も可能な限り脱したい。偉い人に「さすがに軍隊つけてるんだろうな」と言われたんですよ。つまり軍人の護衛をつけて撮影するのがテレビの当たり前だったんですけど、それで撮れる映像なんて何もない。そんな安全な状態の僕に「一口食うか」って聞いてくれるわけがない。
—現地の方にうまく密着するための心構えなどがあるのでしょうか。
上出:相手をリスペクトする姿勢が大事だと思います。現地で暮らしている人たちをリスペクトして接していると、彼らはかなりの確率で心を開いてくれます。そのリスペクトっていうのは、「尊敬しよう!」と構えることではありません。自分の至らなさを自覚するところから始まります。自分が無力であるということを自覚していれば、目の前の誰かを、それも過酷な世界で生き抜く人間をリスペクトせずにいられません。その心は、振る舞いの一つ一つに現れます。そのリスペクトが伝われば、彼らは受け入れてくれて「一口食うか?」って言ってもらえるんだと思います。
―取材映像を見守る小籔千豊さんが、ずっと険しい顔で悩んでいらっしゃる姿が印象的です。なぜただひとりの出演者として小籔さんを選ばれたのでしょうか。
上出:小籔さんなら多角的な視点で観てくれると思いました。キャスティングを間違えたら「かわいそうに、日本で生まれてよかった〜」しか言ってくれないと思うんですよ。ハイパーの映像を観たら「今のままで自分はいいのか?」とか絶対悩むと思うんです。小籔さんが険しい顔でVTRを見てくれているのはすごくよかったなと思います。小籔さんが悩んでいるおかげで、視聴者も悩んでいいんだっていう合図になっているから。それがあるのとないのとでは安心感っていうところでもかなり違ってくると思うので番組としてすごく助けられていますね。
僕らが外の世界へ出る理由
—入社されてから色々な国へ行かれていると思うのですが、学生時代に海外旅行はよくされていたのですか。
上出:海外は結構行ってました。学生時代はバックパックを背負って東南アジアを一ヶ月かけて一周したりしていました。あとはアラスカにテントを担いで行ったりもしましたね。
—上出さんが様々な国に出向かれる中で、旅行にはどのような意味があると考えていますか。
上出:次から次に予想外の事件が起こることが旅の大きな意味かなと思います。だからトラブルをたくさん経験して欲しいですね。なるべくトラブルが起きるような旅を選ぶのがオススメです。受動的な旅と能動的な旅とでは僕にとって喜びの桁が違うんです。だから僕はディズニーランドには行きません。楽しいのは楽しいけど、あれは完成された、与えられた遊びじゃないですか。結局自分で何かを起こしていくことが一番楽しい。綺麗にプランニングされたものをなぞっていったら残るものがないんです。トラブルをあえて見つけに行くって意味では、むしろ雑な旅をしたほうがいいと思います。
―そういったトラブルとあえて出会うためには、危険な場所に行くことが必要なのでしょうか。
上出:安全か危険かっていうのは程度の問題でしかないと思いますよ。例えば、トルコ旅行に1週間行くとしても危険はいっぱいありますし。“安全な旅”なんてないと思った方がいい。それでも色々な意味で旅はしたほうが良いなって思っています。自分が暮らしている世界と違う世界に行けば行くほど、自分がコントロールできないものに触れざるを得なくなっていく。そういう経験はできるだけ多くしたほうが良いと思っています。例えば山に入るだけでも自分がコントロールできない世界が広がっている。いつ雨が降ってきて、いつ動物が出てくるかもわからない。それって海外旅行でも同じなんですよね。自分たちが環境をコントロール出来るというのが自分勝手な思い込みだってことを思い出させてくれる。

—コントロールできない状況に身を置くことが面白い旅につながると。
上出:あとは考えるための物差し、世界を見るための眼差しも必要ですよね。それこそ世界一周のブログをやっている人って大勢いるけど、その中で面白いものを見つけるのはとても難しい。日本にいる時から頭を回していないと海外で色々なもの見ても何も残らないんですよ。
—考えるための物差しを養うためにはどのようにすればいいですか。
上出:僕たちが何かを発見できる場所は「フロンティア」だけです。けれどこのフロンティアっていうのは何も世界の辺境の地のことじゃなくって、例えばこの記事を読んでいる読者の部屋や、通学の電車の中にも溢れています。この肉体の外は全て自分にとってフロンティアだとも言える。知ってる気になっているけれど、世界の99%は僕たちにとって未知の領域です。フロンティアに気づくためには、“自分は何も知らない”と意識することが出発点になるはずです。そして、自分の無知を知るには未知の世界に身を投じるのが一番手っ取り早い。そのために一番簡単なのは、本を読むこと。読書は間違いなく旅そのものです。本を読むことでだんだんと考えるための物差しが生まれる。自分の中にたくさんの物差しを持っていると、実際の旅先で目にするものにたくさんの“違和感”を感じる。想像を覆されることもある。それは相当楽しいし強烈に記憶に残るので、是非経験してもらえるといいと思う。自分の周りのルールとか善悪の向こう側の世界を体感するのは楽しいですよ。
本を読んで、時が来たら旅に出る。それが一番じゃないですか。
~お知らせ~
「ハイパーハードボイルドグルメリポート」の完全新作が4月1日(水)深夜0時12分より放送します。今回はフィリピンの「炭焼き村」に取材。幼い二人の弟を食わせるためにゴミを集め炭を作る少年、ファストフード店の残飯を集める少年少女の一段に密着。

そして、King gnu井口理さん、田原総一郎さんも絶賛の書籍版『ハイパーハードボイルドグルメリポート』が発売中です。番組内に収まりきらない世界の現実を「人が食う」姿を通じて描かれています。
取材/伊藤勇人 文/伊藤拓海・中村健太郎 撮影/南寿希也