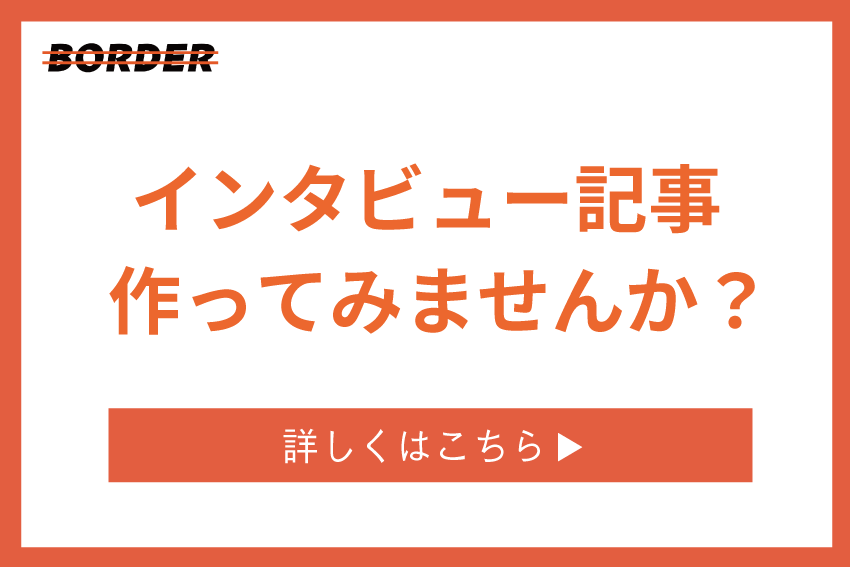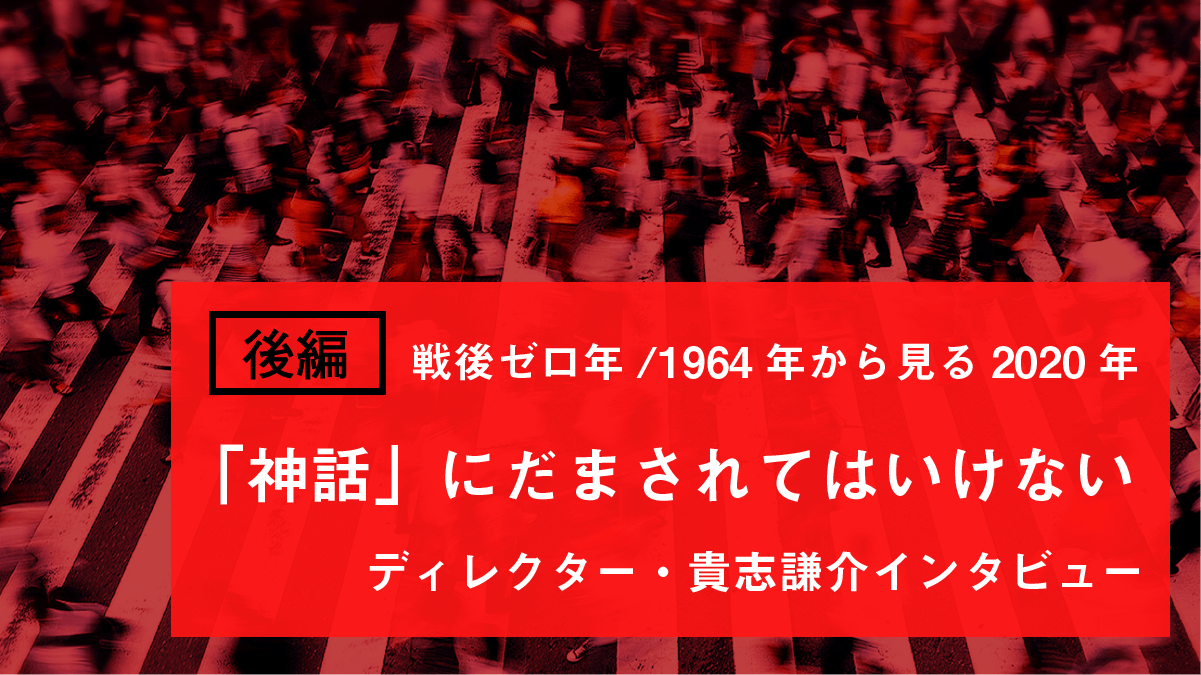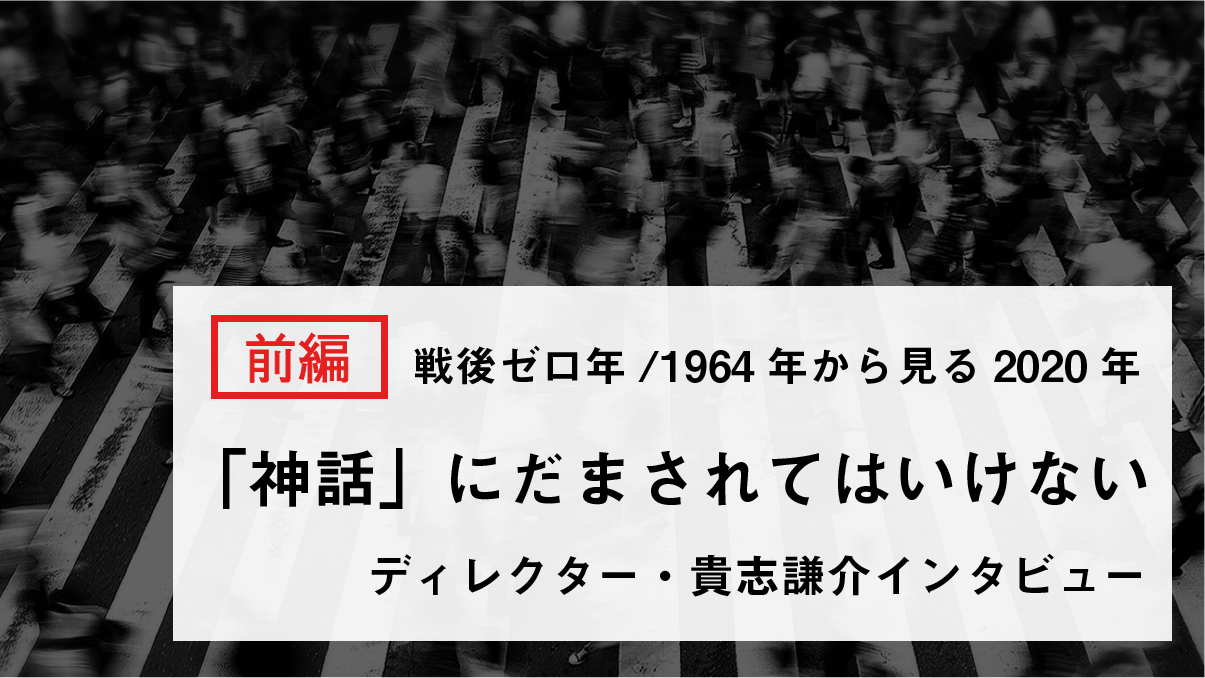渾然としたインターネット社会で『表現』して生きていく フォトグラファー嶌村吉祥丸インタビュー(前編)
フォトグラファーの嶌村吉祥丸さんはファッション誌や広告などの幅広いジャンルで職業として写真を撮り続けている中で、独自の個展を開き写真という表現を通じて社会のあり方を常に考え続けている。誰もがSNSで写真を発信できるようになった状況で、彼は写真という表現をどのように捉えているのだろうか。
前編では、カメラとの出会いと現代における写真という表現媒体の可能性を訊きました。
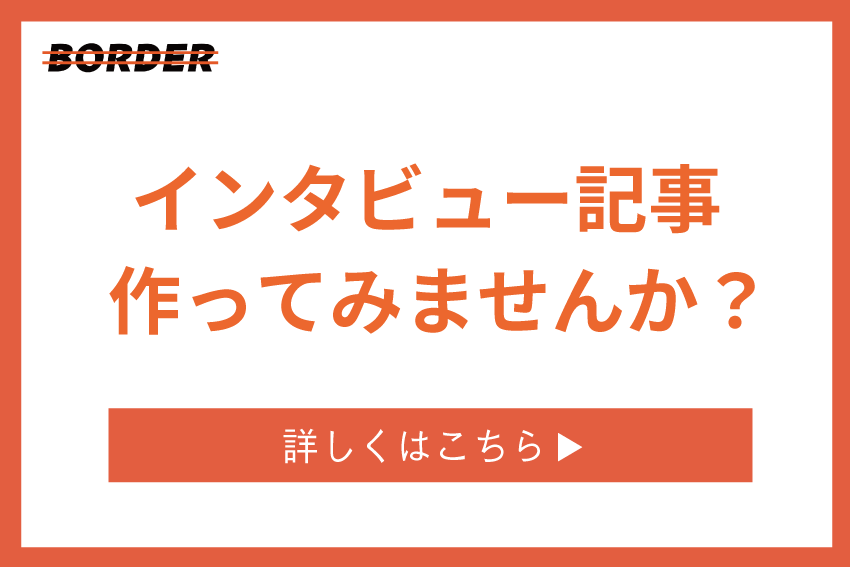
言語としてのカメラ
―カメラとの出会いを教えてください。
嶌村: 大学時代に、祖父の家にあったカメラを借りたことがきっかけです。
―なぜ学生時代にカメラを始められたのでしょうか。
嶌村: 写真を始めた当時、ファッションにも興味を持ち始めていたので、学生時代はファッションに関わる出版サークルで活動したり、会社化には至りませんでしたが古着とコミュニティを中心としたビジネスで起業しようとしていた時期もありました。今ファッションに関わるお仕事をさせていただいているのは、そこが原点だったのかなと思います。
―カメラを始められてから大学2年次には留学されていたそうですね。
嶌村:アメリカのポートランドに1年間留学しました。
―留学先でカメラの地力がついたそうですが、その時からカメラに専念するぞといった気合いはあったのでしょうか。
嶌村:今も当時も専念するぞ、という気持ちはありません。留学先では、写真を通して素敵な人たちと出会えるのが楽しくて写真に夢中になっていました。留学した当初は英語をほとんど話せなかったのですが、写真を撮ることで現地の方々と仲良くなることができました。英語もろくに喋れないのに、写真の力で素敵な人たちと出会い、そのままご飯に連れていってもらったこともありました。今でも、ポートランドや様々な地域のアーティストの方と写真を通して仲良くなったり、彼ら彼女らと情報交換を続けています。時には、政治の話や社会情勢の話をすることもあります。写真を通してオーガニックな人との出会いがつくられ、継続的で健康的な関係を築くことができる、そしてコミュニケーションができるというところではある種、写真は最強の言語とも言えると思います。
―写真を通じたコミュニケーションをする中で気づいたことはありましたか。
嶌村:ポートランドで生活する人たちは、根本的なところから価値観が違っていて、改めて自分が日本人であることを身をもって知りました。最初は文化や価値観の違いに驚きましたが、外の世界で生活し、その土地で様々な人とつながることで、自分の中の”当たり前”が何倍も豊かになった実感があります。個人レベルで人を見れば、日本人と外国人といった境目はなくていいと思いましたし、もっと自由に生きていけばいいと感じました。
―留学後はそのままカメラのお仕事をされていますね。どのように写真のお仕事を受けるようになっていったのでしょうか。
嶌村:有難いことに営業などは一切せずに、人とのご縁でお仕事をいただいています。知り合いから写真を撮ってほしいと依頼されて、そしてその仕事からまたご縁をいただいてお仕事することの繰り返しです。仕事が欲しいとはまったく思わずに、ただ目の前の人との出会いを大切にしていった先に仕事があるだけです。たまたま僕が写真を撮るというスキルを持っていることを出会う方々がなんとなく知ってくださっているので、そういう人とのご縁と自分がいただいた仕事を120%以上で返すことが積み重なっているのかなと思います。
―仕事を受けてもその結果が芳しくなければいつかは仕事が減っていくこともありうると思います。人とのご縁とそれに対するフィードバックだけで仕事が続いていくことは難しいのではないのでしょうか。自分の中でいい写真を撮っていく基準などはあるのでしょうか。
嶌村:仕事として依頼される以上、大枠として最終的なアウトプットがイメージされていることが多いです。つまりある程度枠組みが決められていて、出来上がりの着地点が見えている場合が多い。だからこそ、相手が期待する基準をクリアした写真を撮ることはフォトグラファーとして当たり前のことだと思っています。写真という媒体は人間やオブジェクトと、光さえ存在すれば成立してしまう。相手の期待値までを完璧に満たすのが100%、さらに相手が想定できなかった選択肢を提示することがプラス20%以上の要素だと思っています。どちらかというと、その20%分を僕は大事にしています。相手が想定できなかったgoodな選択肢を提案することは相手にとってネガティブなことではないですよね。1時間で終わるべき撮影に2時間もかけてそれを提案するのはナンセンスですが、限られた時間内で新しいアイデアを提案し続けることで選択肢を増やせたら良いと思っています。
―その20%分の新たな提案にはご自身のオリジナリティーが表れると思います。自分の中にあるオリジナリティーをどのように捉えていますか。
嶌村:オリジナリティーがないことが自分のオリジナリティーだと思っています。カメラマンによっては、「こういう撮影の手法が得意だ」と認識されていることが多いと思っています。この人はモノクロのスタジオ写真が上手だから、そのような写真を撮ってくれるだろうなど。もちろん何か特徴のある武器を持つことも大事だと思いますが、僕自身はフォーマットやテイストの選択はその都度で変えていくべきだと思っています。また、実際に撮るときは何も考えないようにしています。目の前の被写体に対して、いかに直感的にリアクションできるかを大事にしています。また、いただいている仕事の幅をあえて制限せずに、カオスにしようと思っています。ファッション誌に限らず、風景写真やポートレート、CDジャケットや広告などといった様々な領域で活動しています。
―確かにジャンルの幅が広いですね。
嶌村:フォトグラファーの人を紹介するとき、紹介の仕方が難しいと思いませんか。
―確かに、フォトグラファーの方はそもそもさまざまな媒体で多くの写真を撮られているので「この雑誌を撮っているフォトグラファー」のような紹介はあまりされないですね。
嶌村:僕はそのカオスさをあえてつくっているつもりです。写真に特定の色をつけたくないので、逆に全ての色に染まってしまえば何色でもなくなると思っています。そういう意味ではフォトグラファーという肩書きは特定の固定観念を抱きにくく、フレキシブルで面白い肩書きだと思いますね。
―顔出しをされないのも写真に他からのイメージをつけないためでしょうか。
嶌村:写真という媒体がビジュアルである以上、そのビジュアルと作り手のビジュアルをつなげる必要がないと考えているので、そのものだけを見てくれればいいと思っています。
写真で表現する、ということ
―吉祥丸さんは雑誌媒体などでのお仕事と並行しながら、ご自身の個展を開かれています。そしてどの個展のコンセプトにも社会に対するメッセージ性が感じられます。制作されるときに社会に対する意識が含意されているのでしょうか。
嶌村:写真を撮る瞬間は本当に何も考えていないです。写真を撮るときに、いわゆる社会情勢を考えて写真を撮ったところで、目の前に何か風景やオブジェクトがあるだけでドキュメンタリー写真でもないかぎり、直接的にそのメッセージを反映させることは難しいと思います。写真を撮るときは、無意識的な直感を大事にしています。
―個展におけるコンセプトはどのように決めているのでしょうか。
嶌村:日々の生活の中で思いついたアイデアや気になった言葉などのストックの中で、そのときの気分や自分が影響を受けたことからコンセプトが決まって、その受け皿に自分の写真を載せてあげる感覚です。この前の展示[1]では ”photosynthesis” (呼吸すること・光合成について)というコンセプトを軸にして、同時に気候変動の問題を意識していました。当時のタイムリーな問題としてオーストラリアの森林火災が深刻化していたり、たまたま同じタイミングでビーガンに関するドキュメンタリーを観たり、オラファー・エリアソンの作品を見たりしていたので、今まで撮った写真を「光合成」や「呼吸すること」というテーマの上に載せたらどうなるのだろう、という経緯で決めました。




―個展を開く動機は、仕事での写真には出せないような独自の思想や社会に対するメッセージを強く表すためだと思っていましたが、個展の制作においても自然体な印象を受けました。
嶌村:思想や社会的なメッセージは、その匂いがするくらいでちょうどいいと思いますし、こんなgoodはどうですかという提案を一方的に押しつけたくないので、受け取り方は見てくださる方一人一人に委ねています。
―吉祥丸さんの作品とその展示には表現としてのピュアさを感じます。社会に対する強烈なメッセージがなくても表現として成立することを体現されているように思います。
嶌村:オリジナルのアイデアだと思っていた自分の考えですら、過去のアーカイブを見てみたら誰かがすでに同じようなことを実践していたり、特に写真表現は思想的な面でも表現的な面でもすでに様々なアプローチがされています。根詰めて考えていても、どこかで無理が生じてしまうし、何かに回収されてしまうことが多い。だから自分が出会ったものや見たものに対する素直なリアクションから、もっと自然にアウトプットに繋げられたらいいなあと思っています。
―AIから出力されるフェイク画像などが出回るようになり、表現におけるリアルとフェイクの境界が曖昧になってきていますが、写真が持つリアリティはどこから生まれてくると思いますか。
嶌村:そもそもレタッチや合成ができてしまうという意味でも、写真という媒体がフェイクだと言えるかもしれません。ただ、レンズの向こう側の1m, 2m先に被写体があって写真そのものが成立する、という意味では写真は生ものとしてリアリティが感じられる媒体だとも思っています。


―写真から表出される、そこに誰かがいたという事実は、より強いリアリティを感じさせますね。その作品がリアリティを感じさせるかどうかは、作品のつくられ方がリアルかフェイクかという基準では決められないのかもしれないですね。
嶌村:2017年にダミアン・ハーストというアーティストが海底に沈んでいる銅像や難波船を引き上げる様子が記録されたドキュメンタリー映画が公開されました[2]。ただ引き上げた銅像はダミアン・ハーストが引き上げる10年前に実際に海に落としたもので、実は自分が落としたものを自分で引き上げただけのフェイクドキュメンタリーなんです。フェイクなんだけれども、自分が落としたものを自分で引き上げたということは事実であるし、それ自体がドキュメンタリーになっている。
―もはやフェイクが善悪で語られるものではないと。
嶌村:もちろんフェイクによってネガティブなことが起こる場合もあるので、そこは考えなければいけないと思いますが、フェイクであるからこそ私たちに新しい視点を与えてくれる可能性もあると思います。役者の方が役を演じることもフィクションだけれども、それを私たちが見て感情を動かされることもある。そう考えると、リアルとフェイクは分けられるものではなく、リアルという大きい土台の上に何層もリアルとフェイクのレイヤーがあるとも考えれると思います。
―表現をめぐる状況がテクノロジーの発展で大きな変化を迎えているなかで、社会と写真という表現のつながりをどのように捉えていますか。
嶌村:例えば香港でデモがあったときに、実際に香港に行って何か具体的なアクションを起こす人は少ないと思います。しかし、現場で実際に抗議活動をする人、現場の様子を伝えるジャーナリスト、デモの過激さと悲しみを伝える写真家がいるように、それぞれの人間がある事象に対して問題意識を持った場合に、できる範囲のことをそれぞれの立場で考えることが大事だと思っています。各々が関心事に応じて社会と繋がりながら、できることをやればいいのではないでしょうか。写真という媒体には、見た瞬間にその写真が映し出すものに無関心ではいられなくなるような絶対的なリアリティの持つ力があると考えています。絵画やグラフィックのようなアート作品は作品と鑑賞者の間に明確な境界線がありますが、写真が写し出すものはたとえ海外で撮られたものであったとしても鑑賞者が生活している空間と地続きであるということを無意識に自覚しています。そうして、写真とそれを見ている鑑賞者自身の境界を0に近づけることができるとも思っています。
[1]2020年1月18日から2月2日まで開催された個展。”photosynthesis”というコンセプトのもと、人間と環境について、呼吸をすることについて考える展示が構成された。売り上げは環境保全団体を通じてオーストラリアの森林火事災害に対しての自然保護・動物保護などに向けて寄付された。
[2]イギリスの現代美術家であるダミアン・ハーストはサメをホルマリン漬けにした展示「The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living」などの死をテーマとしたセンセーショナルな作品を創り出している。2017年の同氏出演の映画作品は「Treasures from the Wreck of the Unbelievable(邦題:アンビリーバブル号の秘宝)」
嶌村吉祥丸
東京生まれ。ファッション誌、広告、アーティスト写真など様々な分野で活動。ギャラリーのキュレーターも務める。主な個展に”Unusual Usual”(Portland, 2014)、”photosynthesis”(Tokyo, 2020)など。
取材・文/伊藤勇人